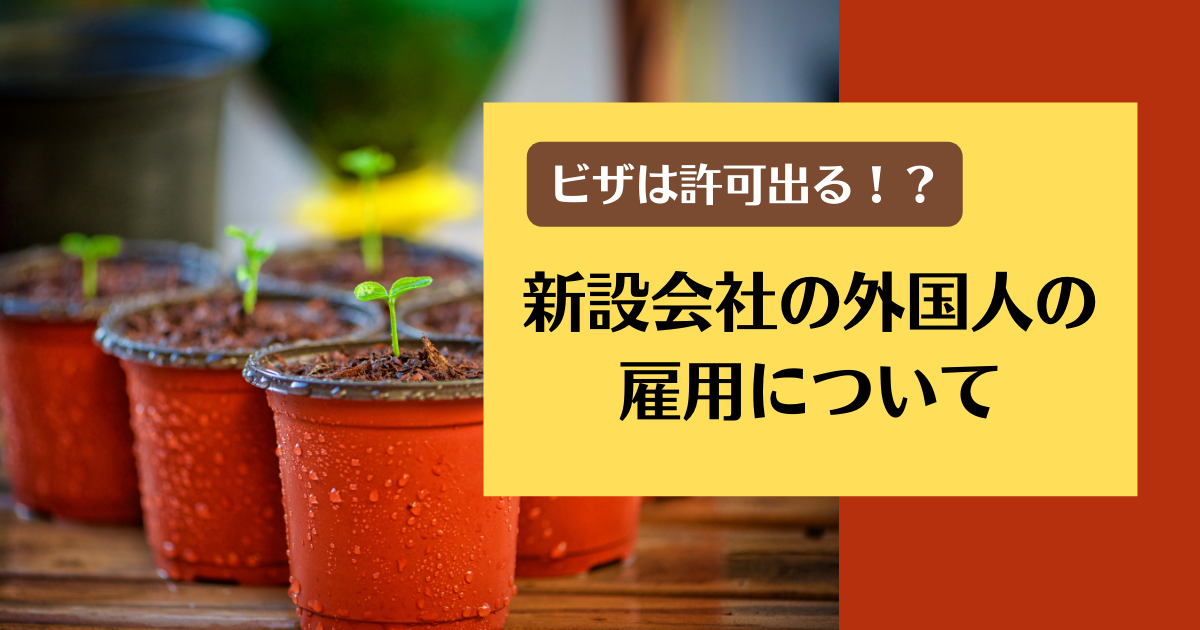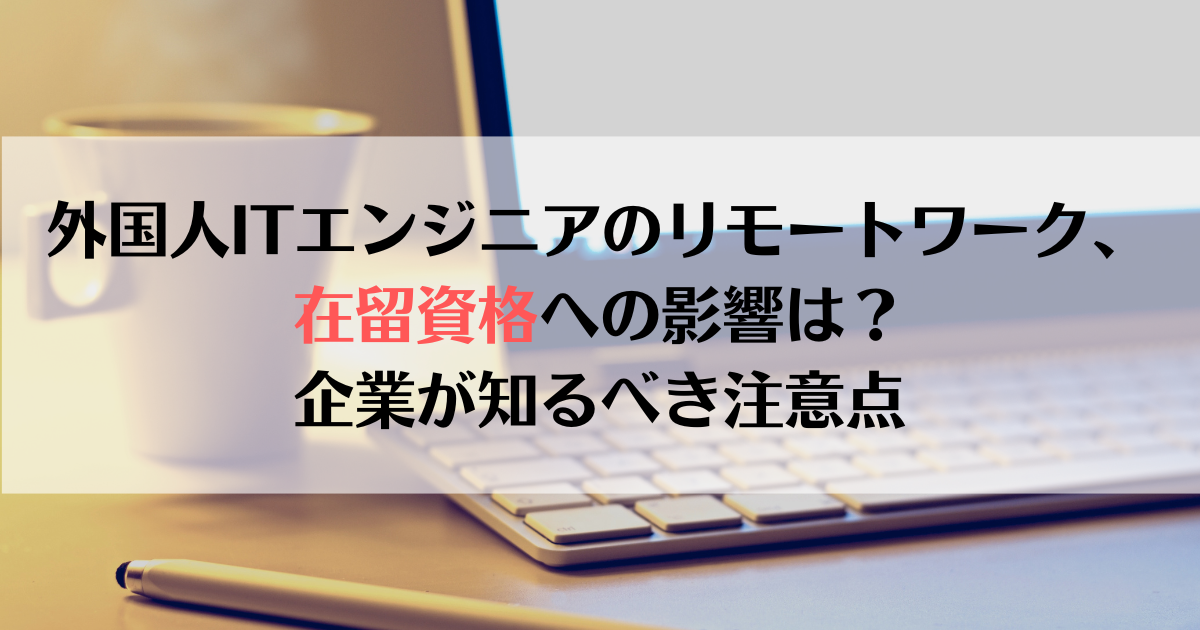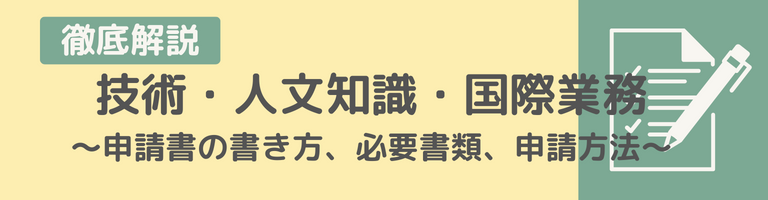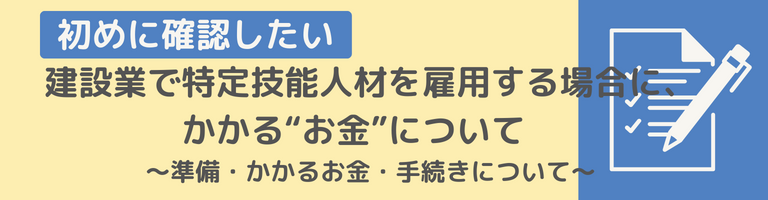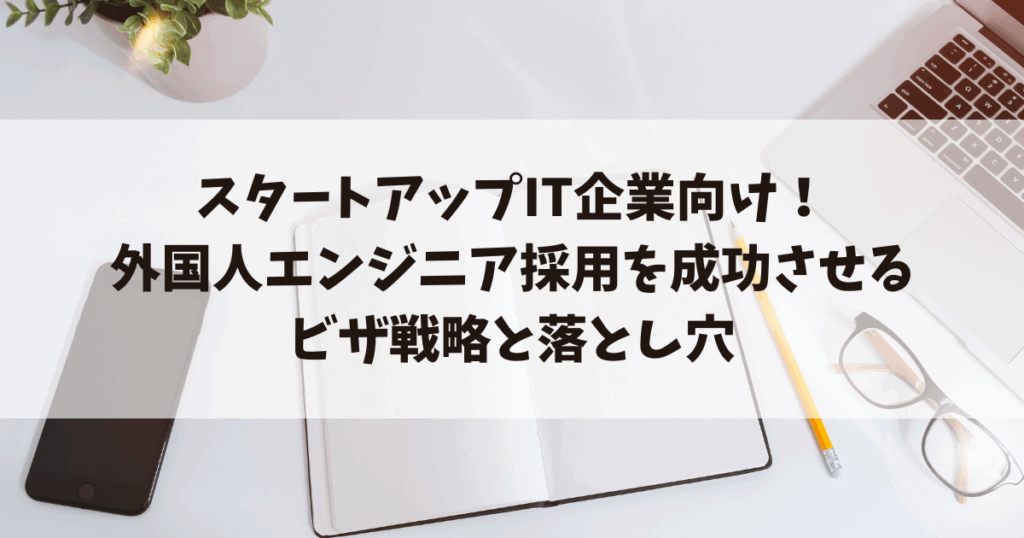
優秀な外国人ITエンジニアを初期メンバーに迎え、事業を一気にスケールさせたい。多くのスタートアップが抱くこの熱意は、成長の大きな原動力です。しかし、在留資格(ビザ)の申請実務においては、その熱意だけでは越えられない、設立間もない企業に特有の「審査の壁」が存在します。大手企業と同じ感覚で申請を進めてしまい、思わぬ不許可に繋がるケースも少なくありません。
本記事では、スタートアップが直面する具体的な審査の壁を明らかにし、それを乗り越えて採用を成功させるための「ビザ戦略」を解説します。
なぜスタートアップの審査は慎重になるのか?

在留資格の審査において、申請企業が設立間もないスタートアップである場合、その審査は大手・中堅企業に比べて、より慎重なものとなるのが実情です。これは、事業を妨害するためではなく、入管が担う「在留管理制度の根幹」に関わる重要な理由があるためです。
審査官が特に重視する、2つの基本的な観点を理解することが、スタートアップのビザ戦略を考える上での第一歩となります。
観点①:事業の「安定性・継続性」
入管審査の最も根底にあるのは、「採用する外国人が、その在留資格で許可された活動を安定的・継続的に行えるか」という視点です。つまり、企業側にその外国人を雇用し続け、約束した給与を支払い続ける経営的な体力があるのか、という点が厳しく問われます。
数年分の決算書によって経営状況を客観的に証明できる既存企業と異なり、設立間もないスタートアップはこの点が未知数です。万が一、事業がすぐに立ち行かなくなり、雇用が維持できなくなれば、来日した外国人の生活基盤そのものが脅かされることになります。
スタートアップの中でも、特に新設会社の場合には、事業運営に必要な許認可を取得し適法に運営できる状態であり、既に取引が始まっているなど企業の継続性に不安が少しでも解消できている状態であれば、就労ビザの取得できる可能性は高まるということになります。
観点②:採用の「必要性・相当性」
次に問われるのが、「なぜ、その事業に、その外国人を採用する必要があるのか」という採用の必然性です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な知識や技術を持つ人材のための在留資格であり、誰にでもできる単純作業は活動として認められません。事業内容がまだ社会的に確立されていないスタートアップの場合、計画している業務に本当に専門性があるのか、そしてその専門性を持つ人材として、なぜ日本人ではなくその外国人でなければならないのか、という点を明確に説明することが求められます。
特にITエンジニアの採用においては、そのエンジニアが持つ特定の技術スキルが、自社のプロダクト開発や事業計画において、どのように不可欠であるかを具体的に示すことがポイントの一つになります。事業計画と採用計画の間に、説得力のある一貫したロジックがあるかどうかが、厳しく見られています。
スタートアップが直面する具体的な「3つの審査の壁」
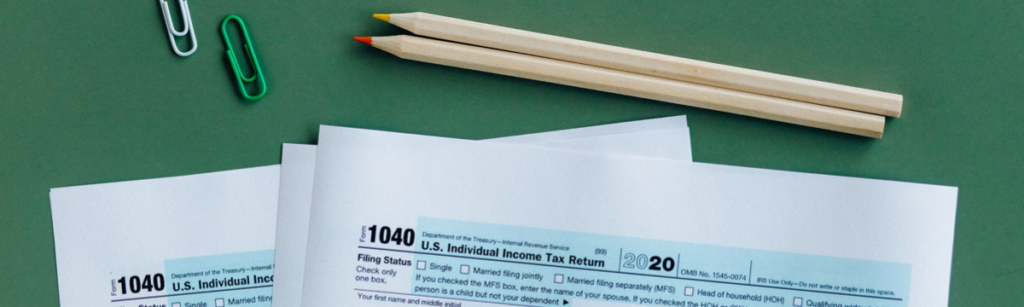
前章で解説した入管の慎重な視点は、実際の申請において、スタートアップ特有の具体的な「壁」となって現れます。ここでは、多くの創業者が直面する代表的な3つの壁と、その本質について解説します。自社がどの壁に直面しうるか、事前に把握することが、効果的なビザ戦略の第一歩です。
壁①:採用の必要性の壁
設会社、特に小規模なスタートアップの審査で最も焦点があたるのが、「採用するエンジニアが担当すべき専門業務が、本当に十分な量だけ存在するのか」という点です。これは、在留期間中、安定的・継続的に専門業務に従事できることを確認するための、極めて重要な審査項目です。
この「業務量」を説明するには、具体的な事業の数字に落とし込むのが最も有効です。 例えば、「現在エンジニア1名で月商500万円だが、取引先増加により来月から月商1000万円が見込まれるため、もう1名増員しなければ開発が追いつかない」といった、売上予測や受注状況に紐づけた客観的な説明が求められます。
そして、この潤沢な業務量の証明は、そのまま次項の「壁②:財務的安定性」を補強することにも直結します。「仕事がたくさんある」ということは、それだけ事業が順調であるという何よりの証拠となり、企業の安定性をアピールする上で非常に強力な材料となるのです。
壁②:財務的安定性の壁
企業の安定性を証明する最も分かりやすい書類は、過去の実績を示す「決算書」です。しかし、当然ながら設立1期目の決算を迎えていないスタートアップには、これが存在しません。この「決算書がない」という事実が、最初の、そして非常に「面倒な」壁となって立ちはだかります。
決算書が無い企業については、企業は今後の事業の見通しを説明するための「事業計画書」の提出をしなければなりません。もし、準備が無い場合にはこの事業計画書の作成が、多くの創業者にとって大きな負担となります。
実際のところは、入管が事業計画の細かな数字の妥当性を精査するわけではありませんが、客観的に見て「もっともらしい」計画書を作成し、提出しなければ申請の土台にすら乗れないのです。この「決算書がないからこそ、事業計画書という追加の書類作成の手間が発生する」という点が、スタートアップが越えなければならない、最初の具体的な壁と言えるでしょう。
壁③:リモートワークの壁
フルリモート体制を導入するITスタートアップも増えていますが、これも一つの壁となり得ます。設立間もない企業がフルリモート体制を採る場合、入管は「本当に組織として機能しているのか」「従業員を適切に管理・監督できる体制があるのか」という点を、より慎重に審査します。
物理的なオフィスという事業基盤がない分、勤怠管理システムの導入、業務報告の明確なルール、定期的なオンラインミーティングの実施、円滑なコミュニケーションを担保するツールの導入など、客観的に証明できる管理体制が具体的に整備されていることが必要になります。
審査の「壁」を乗り越える3つのビザ戦略

前章で解説したスタートアップ特有の「壁」は、決して乗り越えられないものではありません。むしろ、審査官が何を見ているのかを正しく理解し、的確な準備をすることで、むしろスムーズに許可を得ることが可能です。ここでは、審査を突破するための具体的な3つの戦略を解説します。
戦略①:数字とロジックで「採用の必然性」を訴える
スタートアップの申請で最も重要な戦略が、この「採用の必然性」の立証です。「なぜこの外国人を採用する必要があるのか」という問いに対しては、情熱ではなく、客観的な数字とロジックで回答する必要があります。これは、事業計画書とは別に作成する「雇用理由書」で展開するべき、最重要戦略です。
ポイントは、「なぜ日本人ではダメなのか」ではなく、「事業を成長させるために、なぜ今、人員を増やす必要があるのか」を明確に示すことです。
例えば、以下のように具体的な数字を基に説明します。 「現在のエンジニア1名体制での月間売上は500万円ですが、〇〇社との新規契約により、来月からは月間1000万円の売上が見込まれています。既存の体制では、この開発業務を遂行することは物理的に不可能であり、事業計画を達成するために、どうしてももう1名のエンジニアの増員が必要です」
このように、現在の受注状況や具体的な売上予測、今後の開発ロードマップといった客観的な数字に紐づけて説明することで、採用の必要性に圧倒的な説得力が生まれます。このロジカルな説明こそが、審査官の懸念を払拭し、企業の安定性をアピールする上で最も強力な武器となるのです。
戦略②:「形式」と「客観性」を意識した事業計画書の作成
設立1期目の決算書がないスタートアップは、事業計画書の提出が不可欠です。審査官がその内容の細かな妥当性を精査することは稀ですが、だからといって手を抜いてはいけません。
重要なのは、公的機関に提出するに足る「形式」と「客観性」です。事業概要、サービス内容、今後1年間の具体的な収支計画、役員構成などを盛り込み、誰が見ても「もっともらしい」と思える、しっかりとした事業計画書を準備しましょう。この書類が、貴社の事業への真剣度を測る第一の指標となります。
【番外編】「活動状況」を管理する仕組みの明文化
在留資格制度では、許可された「活動」が適正に行われていることを大前提としています。
リモートワークや小規模なオフィス体制の場合、この「活動状況」が外部から見えにくくなるため、企業側がそれを適切に管理する仕組みを持っているかどうかが、実務上、重要なポイントとなります。
申請時に必須とまでは言えませんが、今後の安定的な雇用のためにも、勤怠管理はもちろん、日報や週報などで具体的な業務内容を記録・管理するルールを「リモートワーク規程」等で明文化しておくことが、健全な管理体制を構築しておくこと、より万全です。
まとめ

スタートアップが外国人エンジニアという強力な仲間を迎えるには、情熱やビジョンだけでなく、入管を納得させる客観的な「証拠」と「ロジック」が不可欠です。決算書が無い場合には事業計画書の準備が必要になる場合もあります。
在留資格の申請プロセスは、単なる事務作業ではありません。それは自社の事業と組織体制を見つめ直し、盤石な経営基盤を築く機会でもあります。周到なビザ戦略こそが、優秀な人材を確保し、企業の成長を加速させるための重要な一歩となるでしょう。