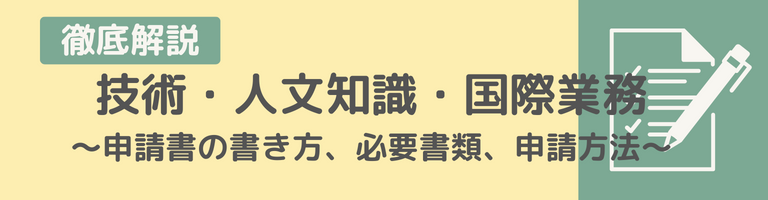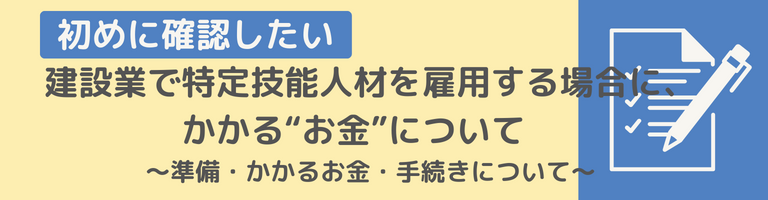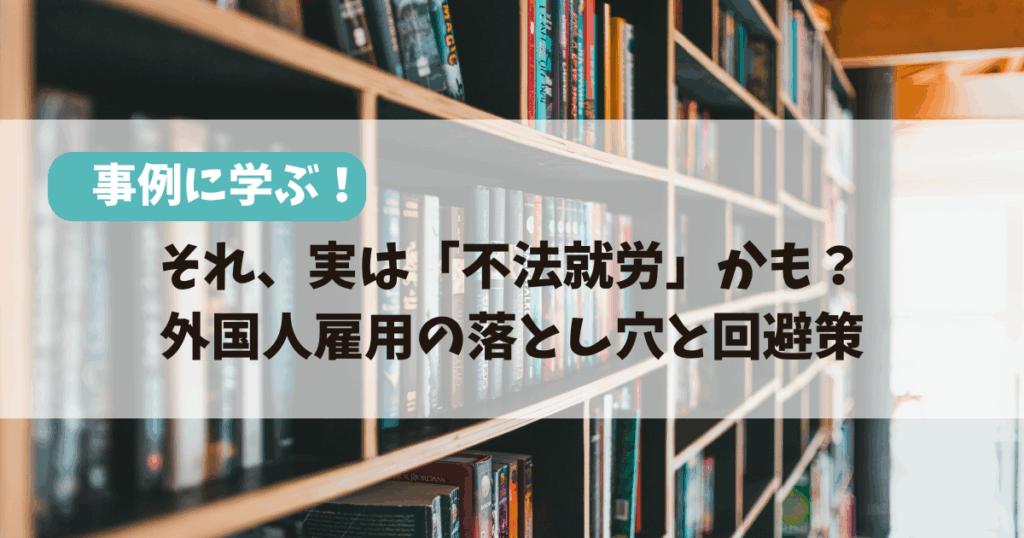
外国人材の採用において、法令遵守は当然の責務です。「うちは法律を守って適正に雇用している」――そう考えている多くの企業にこそ、実は思わぬ「落とし穴」が潜んでいます。意図せずとも、結果的に不法就労に加担してしまった場合、「知らなかった」では済まされず、企業が不法就労助長罪という重い責任を問われる可能性があります。本記事では、実際に起こりがちな具体的なNG事例をケーススタディ形式で紹介し、企業が意図せず法律違反を犯してしまうリスクと、それを防ぐための実践的な回避策を解説します。
【ケーススタディ①】アルバイト留学生の「オーバーワーク」

事例紹介:「週28時間」の壁・優事例に学ぶ!
ITスタートアップのA社は、開発アシスタントとして留学生のBさんをアルバイトで採用しました。Bさんは非常に優秀で日本語も堪能。社員からの信頼も厚く、正社員登用も視野に入れるほどでした。
プロジェクトが佳境に入り多忙を極める中、Bさん本人も「もっと働いてチームに貢献したいです」と意欲を見せてくれました。その熱意に応えたいと思った採用担当者のCさんは、つい、週に35時間ほどのシフトを組んでしまいました。良かれと思っての判断でしたが、これが後に大きな問題へと発展します。
何が問題か?(法的解説)
留学生は「資格外活動許可」を得ることで、アルバイト(資格外活動)が可能です。留学生が取得する「資格外活動許可」は「1週について28時間以内」までというルールがあります(学校の長期休業期間中は1日8時間まで)。この1週というのは、「どの連続する7日間であっても合計が28時間以内」となります。
今回のケースのように、企業がこのルールを知らなかったとしても、週28時間を超えてて働かせてしまうと、その状態は「オーバーワーク」と言われ、Bさんは資格外活動違反で「不法就労」になります。A社は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
ここで最も注意すべきなのは、この「週28時間」という制限は、全てのアルバイト先の合計時間であるという点です。仮にA社でのシフトが週20時間でも、もしBさんが別の飲食店で週10時間働いていれば、合計は30時間です。この場合、Bさんを雇用している全ての企業が、結果的に不法就労に加担していると見なされるリスクを負うのです。
さらに注意が必要なこととして、この資格外活動許可は「『留学』という本来の在留活動があってこその、許可」だという点です。つまり、Bさんが既に大学や専門学校を卒業していたり、あるいは退学・除籍になっていたりする場合、たとえ在留カードの期限が残っていても、学校に通ってない場合には、就労はできないということになります。この場合は、卒業・退学した学生をアルバイトとして雇用することは、時間に関わらず不法就労となります。
企業としての回避策
この落とし穴を避けるために、企業は以下の3つの対策を徹底する必要があります。
① 採用時に「資格外活動許可」と「在学状況」を確認する
採用時には在留カード裏面の「資格外活動許可欄」のスタンプを確認するのに加え、必ず学生証の提示を求め、現在も在学中であることを確認しましょう。「卒業後もまだ在留期限が残っているから」という理由で雇用を継続するのは絶対にNGです。
② 自社でのシフト管理を徹底する
勤怠管理システムなどを活用し、自社での勤務時間が法定の上限時間を超えないよう、厳密に管理することは雇用主の基本的な責任です。
③ 他のアルバイトの有無を確認・申告してもらう
掛け持ちによるオーバーワークのリスクを防ぐため、採用時に「他にアルバイトをしていますか?」と必ず確認しましょう。さらに、「もし他のアルバイトを始める、またはシフトが増える場合は、合計時間が週28時間を超えないよう、必ず事前に会社に申告してください」というルールを設け、本人に署名をもらうなどの対策が不可欠です。
【ケーススタディ②】転職者の「ビザ更新忘れ」と「未手続き」
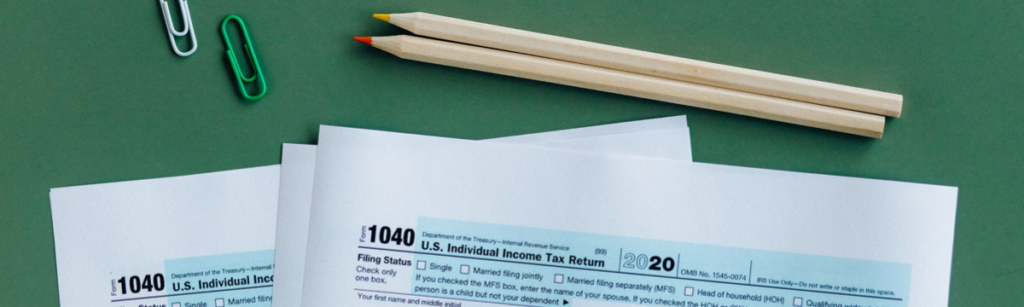
事例紹介:「ビザは大丈夫」を信じた転職者の落とし穴
B社は、他社で実績のあるITエンジニア、Dさんの中途採用を決定。面接でビザの有無を尋ねると、Dさんから「はい、“就労ビザ”はあります」と自信のある返事がありました。
採用担当者はその一言で安心し、在留カードの具体的な「種類」や「有効期限」まで詳しく確認することなく雇用契約を締結。Dさんはすぐに入社し、プロジェクトで活躍し始めました。しかし、この「確認不足」が、後に深刻な事態を招くことになります。
何が問題か?(法的解説)
「就労ビザはあります」という一言の裏には、企業を不法就労のリスクに晒す、主に2つの問題が潜んでいる可能性があります。
1. 在留期間更新の必要があった
Dさんの言葉通り在留資格は持っていましたが、実はB社が入社手続きをした時点で、在留カードの期限が残り数日しかありませんでした。Dさんが単純に更新手続きを失念していたとしても、在留期間が切れた後で雇用を継続すれば、Dさんはオーバーステイ(不法残留)、B社は不法就労助長罪に問われます。
2. 「転職時に変更申請が必要なビザ(在留資格)」だった
あるいは、Dさんが持っていた在留資格は、前職の企業を指定して許可された「高度専門職1号」でした。この場合、たとえ在留期限が十分に残っていても、B社へ転職する際には事前に「在留資格変更許可申請」を行い、B社で働くための新たな在留資格を得る必要がありました。この手続きを怠ってB社で働くことも、許可された範囲外の活動となり、不法就労と見なされてしまうのです。
指定書で就業先が指定される在留資格は、代表的なものに「高度専門職」の他に「特定活動46号」、「特定技能」などがあります。
企業としての回避策
この致命的なミスを防ぐ方法は一つしかありません。候内定者の「ビザはあります」という言葉を鵜呑みにせず、内定後、入社手続きの際に必ず在留カードの「原本」を目視で確認することです。
そして、原本を確認する際は、担当者が自らの目で以下の点を確認する必要があります。
- ① 在留期間(満了日)が十分に残っているか?
- ② 在留資格の種類は何か?
特に②について、「技術・人文知識・国際業務」であれば多くの場合問題ありませんが、「高度専門職」や「特定活動」など、判断に迷う在留資格の場合は、入社手続きを進める前に必ず専門家に相談すべきです。この一手間を惜しんだことが、後に大きな経営リスクへと繋がります。
【ケーススタディ③】業務内容の「範囲逸脱」

事例紹介:「いつの間にか」職務が変更に:業務内容の範囲逸脱
C社は、製品の設計担当として「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つEさんを採用しました。しかし、入社直後に製造ラインで大規模な欠員が発生。
当初は「一時的な応援」として、Eさんにも工場での作業を依頼していましたが、結局欠員は補充されず、Eさんは数ヶ月にわたり、恒常的に梱包や検品といったライン作業に従事することになってしまいました。採用時は設計職だったはずが、いつの間にか実態は現場作業員となっていたのです。
何が問題か?(法的解説)
在留資格は、それぞれ許可された特定の活動を行うために与えられるものです。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、大学などで学んだ専門的な知識や技術を活かす業務(設計、開発、マーケティング等)のための在留資格です。
たとえ当初は一時的な応援のつもりであったとしても、結果的に専門職であるEさんの主たる業務が、誰にでもできる単純労働と見なされる梱包や検品作業になってしまった場合、これは許可された活動の範囲を逸脱した「資格外活動」と明確に判断される可能性があります。
これが発覚した場合、Eさんは在留資格の更新が不許可になるなどの不利益を被ります。繰り返しですが資格外活動違反は不法就労です。Eさんは不法就労となり、指示した企業(C社)も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
企業としての回避策
このリスクを回避するには、経営者から現場まで、全社的な理解と対策が不可欠です。
① 雇用契約書で職務内容を明確に定義する
採用時に交わす雇用契約書や職務記述書(ジョブディスクリプション)で、担当する業務内容を具体的かつ限定的に記載することが第一歩です。「設計業務及びそれに付随する関連業務」のように、活動範囲を明確に定めておきましょう。
② 現場管理職への周知徹底
最も重要なのが、現場の管理職(工場長、チームリーダーなど)に、外国人従業員の就労ルールを正しく理解させることです。「人手が足りないから」という安易な理由で、専門職の外国人を長期間にわたり現場作業に従事させることが、どれほど大きな経営リスクに繋がるかを全社的に共有し、コンプライアンス意識を浸透させる必要があります。
まとめ

今回紹介した3つの事例のように、不法就労は悪意なく、日々の業務の中の少しの油断や知識不足から発生することがほとんどです。「知らなかった」では済まされないのが、不法就労助長罪の怖さです。重要なのは、採用時だけでなく、雇用期間中も従業員の在留資格や活動内容を適切に管理する「体制」を社内に構築することです。自社の管理体制に少しでも不安を感じたり、判断に迷うケースに直面した場合は、問題が発生する前に、最寄りの入管か在留資格に詳しい方にご相談ください。